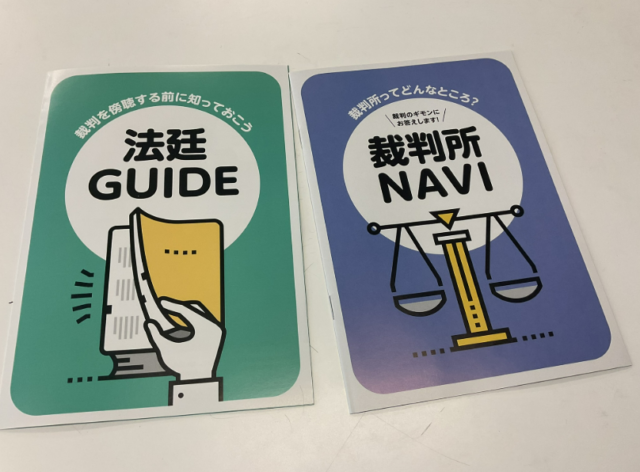クラスを超えて、学年を超えて、自分で選んだテーマについて探究する市邨独自の授業【市邨ゼミ】。
今回は、6月19日(木)の「法律・裁判研究」ゼミの様子を紹介します。
この日は、現職の裁判官をお招きしての授業です!
まず、5時間目には刑事裁判がどのように進んでいくかの説明を受けます。

その上で、6時間目には強盗致傷に関する裁判事例を聞き、グループで量刑を考えました。生徒たちが聞いた事例は次のようなものです。
被告人は18歳の元高校生。
旅行のお金を稼ぎたく、短期高収入のアルバイトに応募するも、実は闇バイト・・・。本人は「これってやばい仕事なんじゃ・・・」という思いを抱きつつも、雇い主(犯行指示役)に身分証を送ってしまっていること、雇い主が体格よく強面な人相なため、怖くて逃げられない状況になります。
そして、空き家の下見、空き巣の見張り役を担った上、戻ってきた家主への暴行を加え大けがをさせるという罪を犯してしまいました。
検察官側の論告求刑では懲役7年の実刑判決が、他方で弁護側は懲役5年執行猶予3年を求めています。
この事例について、生徒たちはグループに分かれて量刑を考えます。



「被告人は実行役から得た報酬2万円を返しているし、相手に負わした怪我の補償も、今後働いて返していこうとしている。」
「高校を自主退学したことも、反省であり事実上の制裁ではないか。」
「犯人グループが怖くて逃げ出せなかったことは考慮してあげないと。」
「でも被害者は厳罰を望んでいる・・・。」
グループ内で活発な意見が交わされました。
自分が考えたこと、グループの他の人の考えたことをデジタルノートにまとめていきます。


模擬事例とはいえ、被告人が18歳であるので、自分たちに置き換えて考えてみた生徒も多いかもしれないですね。
15分程度意見を交わした後はグループで結論を出し、発表します。
量刑の年数に違いはあれども、全てのグループが執行猶予付き判決を出していました。
それぞれのグループの発表のあと、裁判官の方からの講評を頂きました。
高校3年生の生徒たちは18歳。裁判員にも選ばれる年齢です。
司法制度の理解や法に関する理解を深めて法的思考を身につけ、ものごとを公正に判断できるようになっていけるといいですね。
次回の投稿もお楽しみに!